www.youtube.com
⓪大衆には色とりどりの花を|その中に識者にだけわかる芸術をいれるのだ トーマス・マン ゲーテとの対話より
花で読まれているのではないか?
村上春樹の世界は短編小説なんだよ
長編にすると齟齬が生まれるのだ
①キズキと直子とぼくは集合的無意識でつながっている
そしてぼくが緑と近づくほどにその世界が混乱し 幻聴が起こり 最後の一線を越えてぼくと緑の絆が出来上がった時 直子は自殺した
冒頭井戸でみんなつながる
このモチーフはカフカでも騎士団長でもネジ巻鳥でも繰り返される
誰かの無意識が誰かに影響を与える
②長編から来る印象というのが残るかというとそれは確かに残るでも 随所に村上春樹本人が顔を出すから感情移入できない
この文体で書けるのはピンボールまで、羊で限界だったのではないか
堀辰雄の文体でカラマーゾフが駆けないように
チャンドラーやフィッツジェラルド風の会話がわざとらしすぎて腹が立ってくる
いかにもチャンドラーのやりそうな会話を キャラの薄いぼくが使うから
皮肉とエゴを感じる
それを突き抜けても良い話だったけど 未処理でしょう
またディテールが展開しすぎて楽しい短編にはなるけど長編として統合がいまいちか
不要なディテールがたくさんあるように思う 永沢さんとハツミさん、突撃隊なんかなんのために登場したのか?突撃隊はまあ 蛍という短編で元々いたからあれだけど突撃隊の必然は完全に消えている
それに的確にデティールが処理されてないので いったい何の話だったかわからなくなりそう。
レイコさんのレズビアンの少女の話ってなんだ?
そもそもレイコさんってなんだ?最後の年上女性とセックスしたいから登場するのか?
カフカでも50代の佐伯さんとカフカ君がセックスする
③ところでなぜミッシェルではなくてノルウェイの森なんだろうか
なんとなくビートルズで森の雰囲気があればいいのか
ぼくの世代なら ステアウェイトゥヘヴン か ホテルカリフォルニアか。
④キャラ
女は全員同一人物 レイコさんと緑と直子とハツミさん レズビアンの少女にさえにどんな違いがあるのか
男も全員同一人物 キズキ 永沢 ぼくは同じキャラ
全員がぼくの妄想
女性は村上春樹の理想的に都合のいいセリフをしゃべってるだけ
小谷野敦の批評
みんななんでもしそうなキャラだからみんな制限がないからみんな同じになる
ぼくの全セリフを永沢さんが言っても不思議ではない
レイコさんの全セリフをハツミさんが言っても不思議ではない
逆もまた。
表情のないマネキンのような登場人物たち
この世界を稼働させる作者村上春樹のエネルギーだけが 人間くささを出している
⑤どの作品でも女性とすぐ寝る
セックスして射精するのは村上作品では都合よく精神的儀式です
ぜひそんな世界で生きたいものだ(笑)
しかも
相手は必ず美人で賢くやさしく人の心のよくわかる女性
そしてどの作品でも ぼく に男性的魅力は感じないのだがなぜ寝れるかというと
男も女も村上春樹だからだ
まるで実験室のモルモットの観察のように女と寝る
あるいは同時に2人好きになって何が悪いのか?そもそもそれが自然であり
制限は受けないということ
一度に好きになるのは1人だけ、というのは結婚制度を存続させるための共同幻想。
まして男は今目の前にいる女を抱きたいしちょっとかわいくて気が合えば好きになるし
そんな中で最高の女は3~4人はいるものさ
だから好きになろうとセックスしようと直子は直子でとても大切に思っているのだから
誠実ですと 小説中に叫んでいる
娘二人を自殺で失くした直子の両親は葬式で世間体しか気にしないとんでもない人たちとしている
僕の同世代しか人間ではない かくも偏狭に世界を観れば絶望しかなくて
かくも他世代を無視して世界を見れば 行き詰まり 共感はなく うつろになるだろう
さらに
若者の死は美しく重大事件として設定されるが緑の父の死などは 池に住む亀が死んだように語られる 汚いもの どうでもいいものとして処理される
それに直子の父の弟のことで子孫に害がでているように書かれているが
そのまま。直子まで死んだら父は弟のことを思うだろう もっと強く。
こういうのを未処理というと本人は
無意識化の物語を言葉で考えてはいけないみたいに言うから深い井戸に石を投げるようなものだ
⑦コロナの時みたいな精神衛星の潔癖症
一日中手を洗っている
⑧堕落しない 一切の堕落をせずに生きようとしている
坂口安吾の堕落論で行けば 堕落をよしとせずそのまま死ぬのである
特攻隊の兵士は神聖だが帰還すれば闇屋になる
戦争未亡人は聖なる女性だが 戦争が終われば再婚して別の男の子供を生む
でも
だからといってそれを嘆いてはいけない 生きるとはそういうものだ
人間の本性に逆らう偶像を作って人々を操っていたのだ
堕落して本性として生きよう
で
村上春樹のぼくは 堕落を拒否して不自然な人間として永遠の戦地にいるのだ
しかも
あくまで体制側にいるぼく
ちゃんと学校にいき授業に出る どうでもいいことだけどというが
どうでもいいことはちゃんとやるのが村上春樹に主人公
きっと安保闘争に賛成しながら活動には参加せず授業に出たのだろうと思う
昔の日本には勝ち組・負け組はなかった
自分のルートをコースを歩けば全員が引き分けだった
オフコースした人だけが負けたりする
高校も商業も工業も大学も この学校のこの成績だとこういう会社
というルートが出来上がっていて結婚相手もその範囲内
人生は共同体の中で営まれていたのが戦後バブルまでの日本だった
実はよかったのはバブルではなくその直前までの秩序だった
で 安保闘争とはその破壊の祝祭でもあった まあ一揆です
政治的には不合理な活動です だから復権しない
キズキの死も直子の姉の死も直子の死も 必然、災害のようにあきらめるしかない
決して悲しんでいるようには見えない ショックで旅行に言ったとは書いてるけどひとつもショックを受けてない 結局レイコさんとセックスして癒されるという意味不明な。
⑨書評
柄谷行人は、村上の作風を保田與重郎などに連なる「ロマンティック・アイロニー」であるとし、そこに描かれる「風景」は人の意思に従属する「人工的なもの」だと述べた
世界なんかない
すべては村上春樹の内面空間
上野千鶴子は、鼎談集『男流文学論』(小倉千加子・富岡多恵子共著、筑摩書房、1992年1月)において『ノルウェイの森』を論評し、次のように述べている。「はっきり言って、ほんと、下手だもの、この小説。ディーテールには短篇小説的な面白さがときどきあるわけよ。だけど全体としてそれをこういうふうに九百枚に伸ばせるような力量が何もない。
この世界になぜレイコさんや永沢さんやハツミさんが登場するのかは謎だ
面白いけど レイコさんのレズビアンレイプのような話ってなんだ?
富岡多恵子は、上記鼎談集において近松門左衛門の「情をこめる」という言葉を引用し、『ノルウェイの森』について「ことばに情がこもってない」と評する。それは「情をこめるようなことば遣いを現代というのがさせない」からかもしれないと述べている
とにかく堕落しないために正面から真の言葉で語りはしない
見たいものだけを見る その範囲内で沸き起こる感情にだけ関心をもつぼく
中島梓は、『ねじまき鳥クロニクル』について、「面白い」と認めつつも「骨のストーリーだけにしてみるとこれはほとんどどうしようもない三流のレディースコミックみたいなものである。」と述べている
ノルウェイの森も骨のストーリーだけみると
高校時代の自殺した親友の彼女が病んで自殺するまでの間
ぼくは学校生活を楽しみながらちょこっと見舞いに行ったという話になるか
小谷野敦は、『ノルウェイの森』の書評で、「巷間あたかも春樹作品の主題であるかのように言われている『喪失』だの『孤独』だの、そんなことはどうでもいいのだ。(中略) 美人ばかり、あるいは主人公の好みの女ばかり出てきて、しかもそれが簡単に主人公と『寝て』くれて、かつ二十代の間に『何人かの女の子と寝た』なぞと言うやつに、どうして感情移入できるか」と述べている
その意味ではぼくは豪傑だ
そしてそんなことない セックスなんかしたくもない 勉強もしたくもない
といいながらやることはやって楽しくもないとうそぶく最低の人間だ
蓮實重彦は、「『村上春樹の小説は、結婚詐欺の小説である』ということであります。最新作を読んでいなくてもそのくらいはわかる」と述べている
小説世界では女も村上春樹そのものじゃないか
渡辺みえこは、『ノルウェイの森』に登場するレズビアンの少女について、その描き方が差別的であると論じている
それを言えばぼくが認めない人間はサル扱いです
緑の父、直子の両親 施設のおじさんなど みんな影が薄く程度の低い大人として述べられている
www.youtube.com
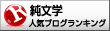
純文学ランキング

